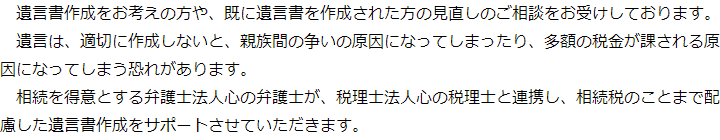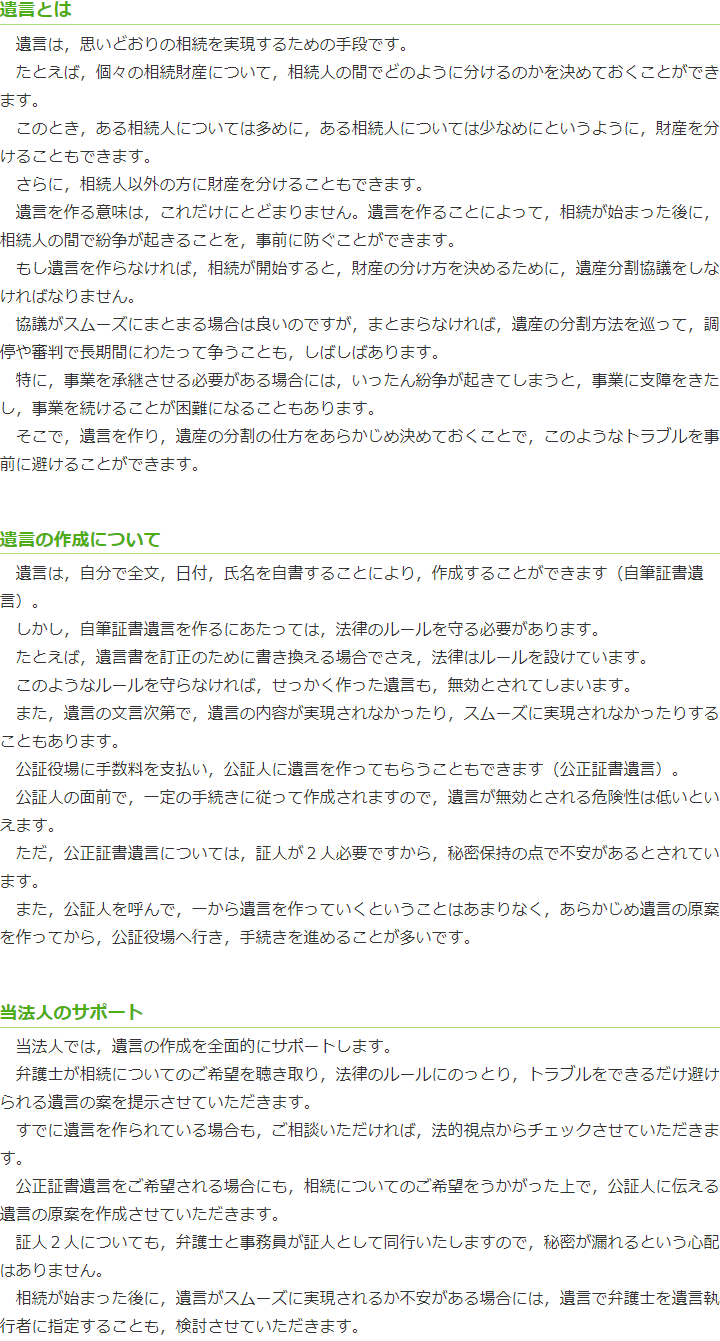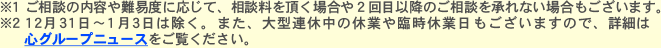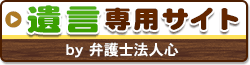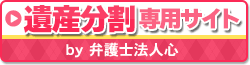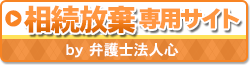遺言
遺言書でできること
1 相続分の指定、遺産分割方法の指定

遺言がない場合は、民法が定めたルールに基づいて、相続人が相続分に基づいて財産を引き継ぐこととなります。
相続人の合意がある場合は、相続分とは異なる分け方にすることもできますが、そうでない場合は、相続分をベースに各自が引き継ぐ財産が決まってしまいます。
たとえば、遺言がないと、原則、子の相続分は均等になる等、杓子定規なルールが適用されることとなってしまいます。
ただ、現実には、特定の子に多くの財産を取得させたい等、相続の割合を変更したいと考えることもあると思います。
そのような場合には、遺言を作成し、各自の相続分をあらかじめ指定することができますし、さらに具体的に、誰がどの財産を引き継ぐかを決めてしまうこともできます。
このように、遺言を作成すると、相続人で遺産分割を行うに当たり、相続分を指定したり、遺産分割方法を指定したりすることができます。
2 遺贈
遺言では遺贈について定めることができます。
遺贈とは、自身が亡くなったときには、ある人に相続財産の一定割合を取得させたり、特定の相続財産を取得させたりすることを言います。
遺贈の重要なポイントは、相続人以外であっても、相続財産を取得させることができるということです。
遺言がないと、相続財産は相続人にのみ引き継がれることとなりますが、遺言があると、相続人以外に相続財産を引き継ぐことができることとなります。
このように遺贈について定めることも、遺言書のみに認められた機能になります。
3 認知
いわゆる婚外子については、父子関係があることを公的に明確にするためには、認知を行う必要があります。
認知を行わなければ、公的に父子関係を証明することができず、たとえば、相続権を主張することもできないこととなります。
認知については、生前に行うこともできますが、遺言で認知について定めておき、死後に認知を行うことも認められています。
このように、死後認知についても、遺言のみに認められた役割になります。
4 祭祀承継者の指定
墓や仏壇等の祭祀財産については、相続財産とは異なるルールで引き継がれることとなります。
祭祀承継者は、第一次的には、被相続人が指定することとなっており、被相続人の指定がなお場合は慣習で定めることとなり、慣習でも定まらない場合は家庭裁判所の審判で定まることとなります。
自身が被相続人となったときに備えて祭祀承継者を指定すること場合は、文書や口頭でも定めることもできますが、遺言によっても定めることができます。
5 生命保険金の受取人の変更
生命保険金の受取人は、保険契約の中で決められることが多いです。
受取人の変更をしたい場合も、多くの場合は、保険会社に問い合わせを行い、受取人の変更を行うこととなります。
とはいえ、生前に保険会社で手続を行うことは避け、秘密裏に生命保険金の受取人を変更することとしたいと考えることがあります。
過去にも、保険会社の職員が特定の親族と懇意にしているため、保険会社には分からないように、保険金の受取人を変更したいとのご相談をいただいた例が存在します。
このような場合には、遺言で生命保険金の受取人を変更することも考えられます。
6 遺言執行者の指定
このように、遺言では、様々な種類の定めを設けることができます。
ただ、このような定めを置いたとしても、きちんと遺言の内容が実現されなければ、意味がありません。
遺言内容の実現は、財産を取得するものとされた人等、遺言により利益を受ける人の方で行うことができる場合もありますが、一定の場合には、代わりに遺言内容を実現する人が必要になってくることがあります。
このような場合には、遺言執行者を指定しておき、その人に遺言執行者に就任してもらうことにより、代わりに遺言内容を実現してもらうことができます。
たとえば、不動産の遺贈がなされた場合については、相続人全員が手続に協力しなければ、遺贈の登記を行うことはできませんが、遺言執行者がいる場合は、遺言執行者の協力を得られれば、遺贈の登記を行うことができます。
認知についても、遺言執行者が手続を行うこととされています。
遺言執行者については、遺言によってのみ定めることができるとされています。
このため、遺言執行者を指定しておきたい場合は、遺言にそのための条項を設けておく必要があることとなります。
遺言の落とし穴
1 弁護士が説明する遺言の落とし穴

遺言には、様々な落とし穴があります。
過去の事例では、専門家が作成した遺言であっても、このような落とし穴に嵌まってしまっている遺言が見受けられます。
そのため、遺言について専門家に相談する場合は、遺言に強い弁護士にご相談いただくのが良いでしょう。
以下では、専門家が作成した遺言について、このような落とし穴に嵌まってしまっていた実例を説明したいと思います。
2 相続人が被相続人よりも先に亡くなり遺言が無効になってしまったケース
⑴ 3人の子どもがおり、長男とその子どもに相続させる遺言を作成
祖父には3人の子どもがいます。
長男である父は、私を含めた家族とともに、祖父と同居しており、長年にわたり、祖父の生活を支えてきました。
次男と三男である叔父は、長年祖父と会っておらず、疎遠になっています。
祖父は、長年同居してきた私たち家族に遺産を相続させたいと考え、専門家に相談し、遺産の大部分を父に相続させるという遺言を作成し、保管しておりました。
祖父は、私たち家族にも、遺言の内容を話しており、私たちも遺言の内容どおりの相続が行われるものと思っておりました。
⑵ 被相続人より先に相続人である長男が亡くなった
その後、私の父が急死し、その数年後祖父が亡くなりました。
相続についての話し合いが始まると、祖父の二男と三男である叔父が、自分たちには法定相続分があり、遺産の1/3をもらえるはずだと主張してきました。
私は、父の子であり、父の財産を受け継ぐ地位にあるはずです。
私は、叔父のこのような要求を呑まなければならないのでしょうか?
民法は、法定相続分を定めています。
遺言が残されていない場合には、法定相続分を基準として遺産分割が行われるものとされています。
事例のように、3人の子どもがいる場合には、1人当たりの法定相続分は、1/3となります。
事例の叔父の主張は、法定相続分を前提としたものです。
もちろん、被相続人が、遺言で、法定相続分と別の決め方をしている場合には、法定相続分のルールは適用されず、遺言のとおりに相続が行われることになります。
そうしますと、祖父の、遺産の大部分を父に相続させるという遺言が、有効かどうかが問題となります。
⑶ 遺言の有効性について
法律上の原則として、被相続人が亡くなった時点で、生存していない方は相続人となることができません。
ですから、事例では、父は既に他界しているため、相続することができません。
また、父が亡くなったことにより、その子どもが代襲相続できるのではないかということが争われたこともありましたが、判例は、特段の事情のない限り、代襲相続を認めることはできないとしています(最判23年2月22日)。
ですから、事例の、父に事業用資産を相続させるという遺言は、父が亡くなったことにより、原則として、意味を失うことになります。
⑷ トラブルを防ぐための対策
それでは、このようなトラブルを防ぐためには、どうすれば良かったのでしょうか。
まず、相続人である父が死亡したときに、新たに遺言を作り直すということが考えられます。
しかし、実際には、相続人が死亡したときには、被相続人が認知症などになっており、遺言を作り直せる状態ではないということが、しばしばあります。
結局のところ、遺言で、相続を受ける方が先に亡くなった場合のことを決めておかなかったことが、事例のトラブルの原因であるということができます。
遺言で、「○○が遺言者の死亡以前に死亡したときは、前条により○○に相続させるとした財産を、××に相続させる。」という条項を加えておけば、そうしたトラブルは防げたはずなのです。
このように、相続で失敗しないためには、トラブルを想定しつつ、前もってそのトラブルを防止できる手立てを打っておく必要があります。
相続で失敗しないためにも、一度信頼できる弁護士に遺言をチェックしてもらうことをおすすめします。