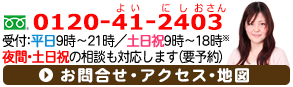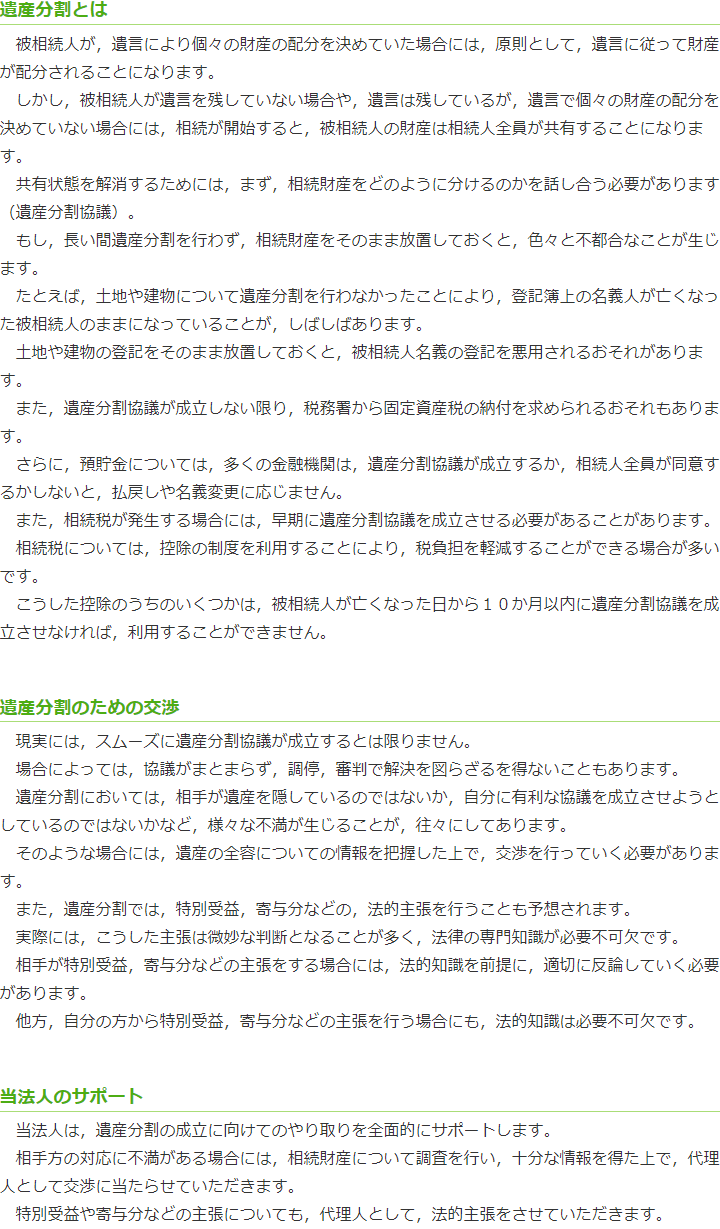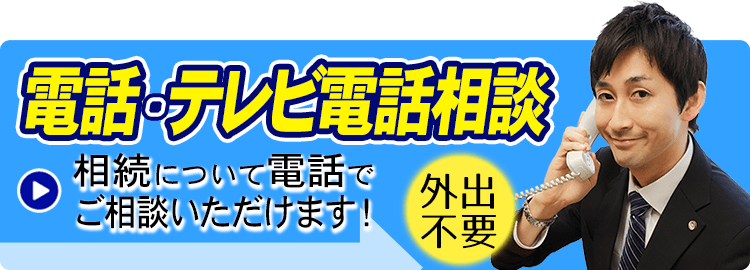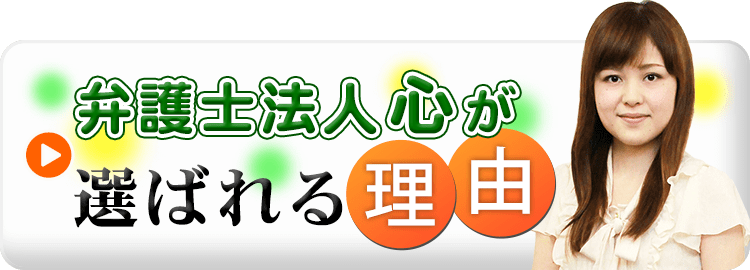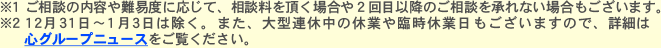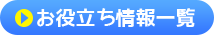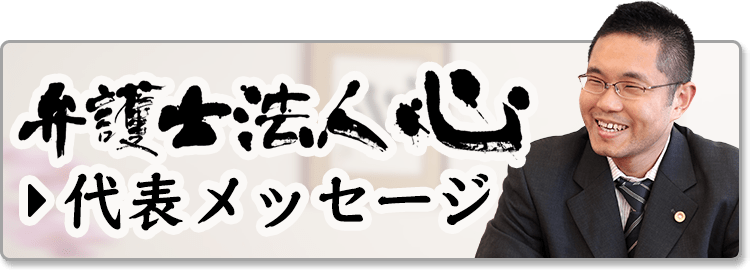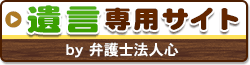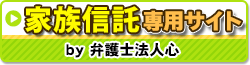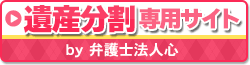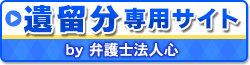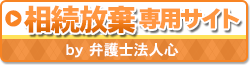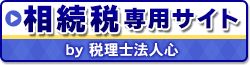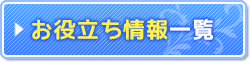遺産分割協議
不動産の売却を予定している場合の遺産分割
1 不動産の売却を予定している場合

相続した不動産について、第三者への売却を検討することがあります。
例えば、相続した不動産を誰も使用していない場合には、不動産をそのままにしておいても、管理の負担だけが生じることから、第三者への売却を検討することがあります。
また、相続した債務を返済したり、相続税を納付したりする必要がある場合には、返済資金や納付資金を調達する必要があり、その際、不動産を売却して、返済資金や納付資金に充てることを検討することがあります。
このように、第三者への売却を検討している場合に用いられる遺産分割について、複数の方法を説明したいと思います。
2 換価分割の方法を用いる場合
⑴ 換価分割について
相続人が共有しているままの状態で不動産を売却し、売却代金を相続人間で相続分等に従って分割する方法を換価分割といいます。
⑵ 換価分割のメリット
不動産の売却代金を相続分等によって分割するのに合わせ、不動産の売却に要する経費、不動産の売却により発生する税金を相続分等によって分担することができます。
換価分割の場合は、基本的には、これらの経費や税金を売却代金と同じ割合で分担することとなります。
この点において、換価分割は、相続人間の公平感の高いというメリットがある遺産分割方法であると言えます。
経費や税金の内容は以下のとおりです。
ア 不動産売却に要する経費
不動産業者へ支払う仲介手数料、土地の測量費用、建物の取壊費用等があります。
イ 不動産売却により発生する税金
譲渡益に課税される所得税、住民税等があります。
また、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料を負担している場合には、譲渡益の発生により、負担額が増額されます。
⑶ 換価分割のデメリット
相続人全員が、売買契約書に実印を押印し、3か月以内の印鑑証明書を提供しなければ、売却の手続きを進めることができないという問題があります。
こうした問題を避けるために、相続人のうちの1名を代表者とし、不動産を代表者の名義にした上で、代表者から第三者に対して不動産を売却する方法が用いられることもあります。
とはいえ、このような方法を用いる場合であっても、いくらで不動産を売却するかについて、他の相続人の同意を得る必要があると考えられます。
このため、相続人の中に協力的ではない人がいる場合には、売却の手続きがスムーズに進まないおそれがあります。
最悪の場合には、買主が見つかり、売買契約書を作成したにもかかわらず、その後、相続人全員の協力を得ることができなかったため、買主への名義変更を行うことができず、数百万円の違約金を支払わなければならなくなるケースもあります。
この点が、換価分割のデメリットとなります。
3 代償分割の方法を用いる場合
⑴ 代償分割について
特定の相続人が不動産を取得し、その相続人が不動産を売却して売却代金を取得する代わりに、その他の相続人に対して代償金を支払うという方法を代償分割といいます。
⑵ 代償分割のメリット
不動産を取得した特定の相続人が売却の手続きを行うこととなり、その他の相続人の協力や同意を得る必要がないこととなります。
このように、単独で売却の手続きを進めることができ、手続きの確実性が高まるという点において、メリットがあります。
⑶ 代償分割のデメリット
売却に要する経費、売却により発生する税金については、不動産を取得した特定の相続人が単独で負担することとなります。
また、不動産の購入を予定していた人が融資を受けることができなかった等の理由により、売却が途中でキャンセルとなった場合には、不動産を取得した特定の相続人において、別の購入予定者を探さなければならなくなるリスクもあります。
このように、不動産を取得した特定の相続人が経済的負担、リスクを負うこととなる点において、相続人間の不公平感が生じる可能性があるというデメリットがあります。
遺産分割の流れ
1 遺言書の有無を確認する

被相続人が遺言書を作成していた場合には、基本的には遺言書に従って遺産を分けていくことになります。
そのため、まずは被相続人が遺言書を残していないか、確認しましょう。
2 相続人の調査をする
遺言書がない場合には、遺産分割協議を行い、相続人の間で遺産をどのように分けるか、話し合う必要があります。
相続人全員が一堂に会する必要はありませんが、相続人全員の同意を得る必要があり、相続人が一人でもかけていると、せっかく合意に至っても、遺産分割協議は無効となってしまいます。
そのため、遺産分割協議を行うにあたり、相続人全員を把握し、漏れがないようにしましょう。
3 相続財産の調査をする
相続人が確認できたら、次はどの財産が遺産となるのか、調査をしましょう。
被相続人がどこに不動産を持っていたか、どの金融機関に預貯金を持っていたか、いくら持っていたのか等、分割を行う前に十分に調査を行います。
遺産分割協議を行った後に新たに相続財産が見つかった場合には、その相続財産についてまた遺産分割協議を行う必要が生じてしまいます。
この際に争いになって合意が形成できない、ということもあり得ますので、事前に十分に相続財産を調査しましょう。
4 遺産の評価を決める
不動産や株式など、直ちには具体的な額が決まらない相続財産がある場合には、遺産の分け方を話し合う前提として、これらの財産について、金銭的な評価を行います。
遺産分割の際、評価額をめぐって争いとなることも少なくありません。
不動産の場合、固定資産税評価額、路線価、時価など、いろいろな評価方法があると思いますが、どのように金銭的評価するのか、相続人間でよく話し合いましょう。
5 分割割合、分割方法を決める
遺産分割協議の中では、誰がどれくらい遺産を受け取るのか(分割割合)、代償分割や換価分割等どのように遺産を分けるのか(分割方法)などについて、相続人の間で話し合います。
不動産を取得したい相続人がいるか否か、遺産にどのような財産があるかなどを踏まえて、相続人全員が合意できるような分割の方法を検討しましょう。
6 遺産分割協議書の作成
相続人全員の間で話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成しましょう。
相続登記や口座の解約手続きなどでも使う書類になりますので、内容や記載方法には注意をしましょう。
内容や書き方に不安がありましたら、一度専門家にご相談いただければ、疑問点や不安の内容に即した助言を得ることができるかと思います。