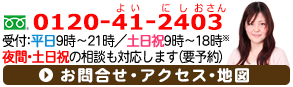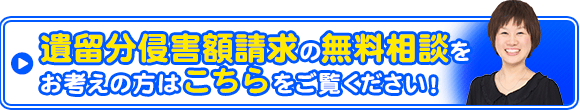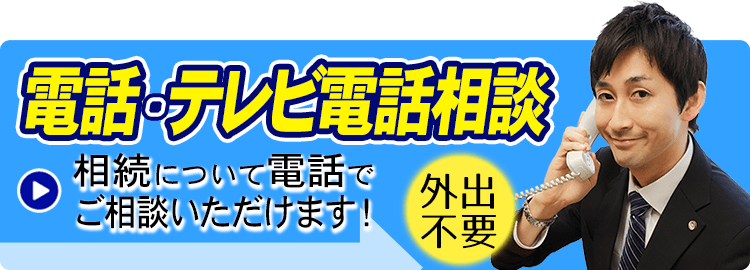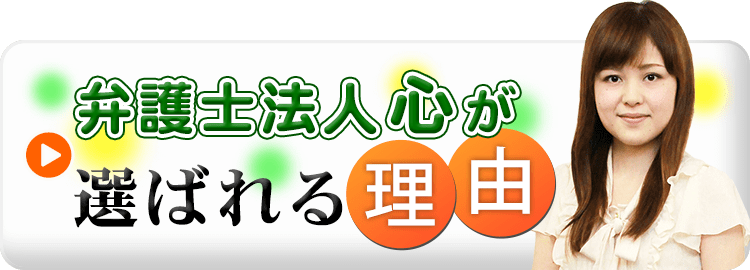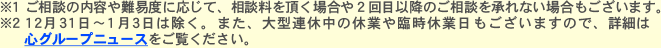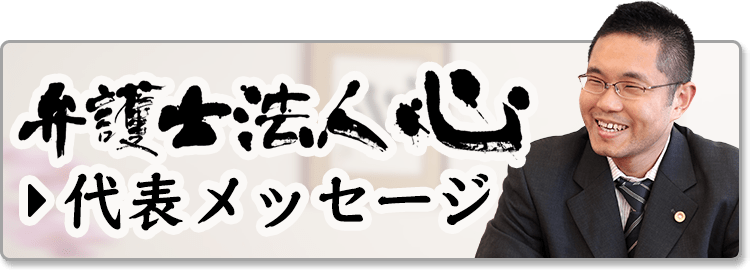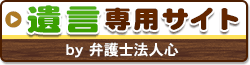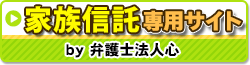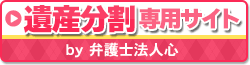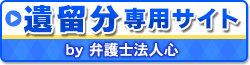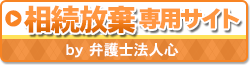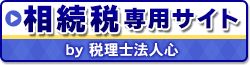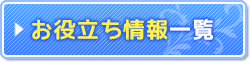遺留分侵害額請求の流れ
1 遺留分侵害額請求の方法
遺留分侵害額請求権は、意思表示の方法によって行使されます。
つまり、遺留分を有するとしても、財産を残された受遺者や受贈者に対して遺留分侵害額請求権の行使をする意思表示をしないと、金銭を請求するための請求権は発生しません。
そして、遺留分侵害額請求権は、遺留分を持つものが、相続の開始と、遺留分の侵害に当たる贈与や遺贈があったことを知ってから1年間行使しなかった場合、消滅時効の援用により消滅します。
相続が開始してから10年経過した場合も同様です。
遺留分侵害額請求の行使は裁判による必要はなく、遺留分があることを主張し、財産を残された人がその分について金銭を支払うという方法によっても遺留分については解決することができます。
2 具体的な遺留分侵害額請求の手続きの流れ
⑴ 調査
保障される遺留分は相続財産の価値、相続人が直系尊属のみか否か、法定相続人の数によっても異なり、その遺留分について、被相続人による生前贈与や遺贈で侵害されていないか調査します。
つまり、遺留分侵害額請求をするためには、当該相続の全体について把握する必要があるのです。
⑵ 意思表示
⑶ 協議
当事者間で協議し、受遺者・遺贈者が遺留分について納得し、侵害分を支払ってくれるのであれば、ここで手続きは終了します。
⑷ 調停
当事者間での話し合いがうまくいかない場合には、家庭裁判所へ遺留分侵害額調停を申し立てることになります。
そこで、中立的な調停委員や裁判官を間に立てて話し合いを行い、そこで、合意がなされれば、調停調書を作成し、解決が図られます。
⑸ 訴訟
調停において合意に至らないような場合には、最終的な民事訴訟となり、遺留分侵害額請求訴訟を提起し、判決を求めます。
判決を待たず、和解も可能です。