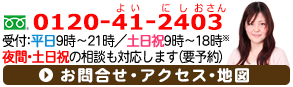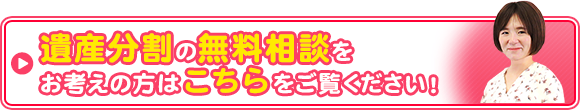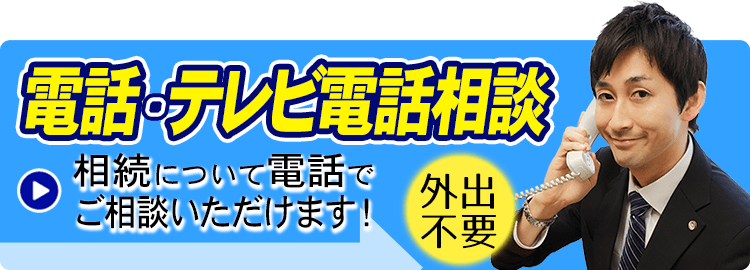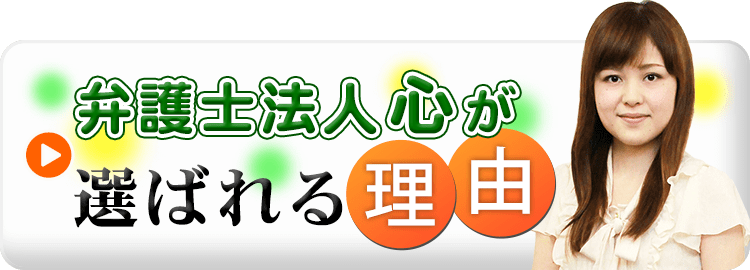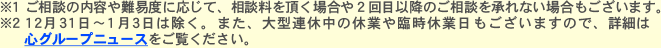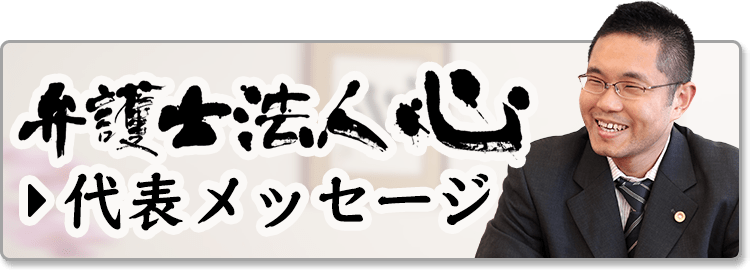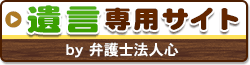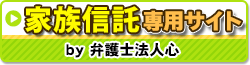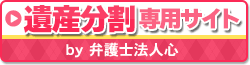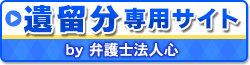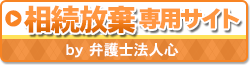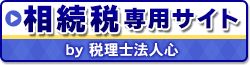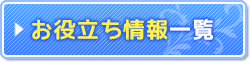遺産分割後に遺言が見つかったら、どうすればよいですか?
1 基本的に遺産分割協議より、遺言書の方が先に有効となる
遺言書は、遺言者の死亡の時から効力が生じます。
遺産分割協議が被相続人(亡くなった人、遺言者と同一人物)が亡くなった後に、相続人が被相続人の財産の分配等について協議を行う以上、遺産分割協議は原則、遺言書の効力が生じた後に行われることになります。
そのため、基本的には相続人間で行われる遺産分割協議は、遺言書により被相続人の財産等について、相続人の相続分を指定したり(902条1項)、遺贈(964条)などで、その帰趨が決められているあとに行われることになります。
言い換えれば、遺産分割協議が行われるころには、遺産分割協議を行うべき被相続人の財産は、遺言書によって分けられて、協議すべき被相続人の財産はなくなっているような状態になります。
そのため、基本的には、遺言書が存在する場合の遺産分割協議は有効なものとしては扱われず、遺言書の内容が優先されます。
しかしながら、上記説明のとおり、すでに遺言書でその財産がどのように分けるか決められていることが前提ですので、➀遺言書が有効でない(形式不備などで)、②遺言書に書かれていない財産があり、その分について遺産分割協議を行った、場合などは遺産分割協議が必要となります。
以下、そのような例外的事情がないことを前提に説明します。
2 相続人全員の同意があれば有効な遺産分割協議が可能
遺言書があったとしても、相続人全員で合意をすれば、遺言書の内容とは異なる内容の遺産分割協議を行うことは、基本的に可能です。
法律上そのことを明示しているものはありませんが、そのような取扱がなされることが多いです。
遺言書は被相続人の最後の意思表示といってもよく、その内容についてはできる限り従うようにするべきですが、遺言者が遺言書を作成したときと事情が異なっていることもありますし、遺言書について直接影響を受けうる人である相続人全員の合意があるのであれば、遺言書と異なる内容の遺産分割協議を有効とした方が柔軟な問題解決を行うことも可能になるからです。
そして、遺言書の内容とは異なる遺産分割協議を行うためには、相続人全員で遺言書の内容を確認し、その内容とは異なる遺産分割協議を行うのかについて意思確認を行う必要があります。
3 相続人の合意があったとしても遺産分割協議の有効性が問題となるケース
⑴ 遺言執行人が選任されており、追認しない場合
遺言書には、その遺言書を執行する人間(遺言執行人)が指定されている場合があり(1006条1項)、その執行のためになされる処分や執行を妨げるような行為を行ってはいけません(1013条)。
そのため、遺言書より、遺産分割協議を行う場合は、その執行人の追認(同意)も必要となると考えられています。
そのため、遺言書と異なる遺産分割協議内容について遺言執行人の同意が得られない場合は、原則とおり遺言書の内容が優先され、遺産分割協議は無効となる可能性があります。
⑵ 遺言書による認知がなされた場合
遺言者は遺言書によって、婚姻関係にない相手との間にできた自分の子どもの認知を行うことができます(遺言認知、781条1項)。
認知がなされた場合出生にさかのぼってその効力が生じますので(784条)、その認知された子も被相続人の子になるということになりますので、既に行われた遺産分割協議は「相続人全員の合意」ではないということになりますので、その遺産分割協議は無効となります。
もし、遺言書とは異なる内容での遺産分割協議をそれでも望むのであれば、その子を含めた相続人全員で再度合意をする必要があることになります。
⑶ 相続人以外の第三者に贈与がなされている場合
遺言書では、相続人以外の第三者に対して遺贈をすることが可能であり、遺言書にそのような遺贈の内容を含んでいる場合は、相続人の一方的な都合で遺贈を受ける人(受遺者)の権利を奪うことはできませんので、その内容に反する遺産分割協議は基本的に無効となります。
逆に言えば、受遺者の同意があれば、遺言書の内容と異なる遺産分割協議も有効になります。
受遺者は、遺言者の死亡後、基本的にいつでも遺贈の放棄を行うことができますので、受遺者がその放棄をしていた場合は、基本的その受遺者の合意は不要となります。
一方で、単なる贈与ではなく、包括的に遺贈を行われている場合(「相続財産の1/5を遺贈する」など)は、その受遺者が相続について放棄をする場合は、その受遺者は遺贈を知ったときから3か月以内に家庭裁判所の相続放棄を行う必要がありますので、注意が必要です。
⑷ 相続人廃除がなされていた場合
遺言書では、本来相続人であった人(推定相続人)を廃除することで、相続人である地位を失わせることができる場合があります。
そのような廃除に関する規定が遺言書にあった場合は、行われた遺産分割協議は相続人の地位を失った人を含んだ合意がなされている可能性がありますので、有効とはならない場合があります。
4 遺言書を隠してはいけない
これまでの説明で、「相続人全員の同意があれば問題なら、遺言書には、遺言執行者も、遺贈も、認知も廃除もないし、自分達はどうせ合意するから、遺言書を隠してしまおう。」と考えることは危険です。
自己に不利益な遺言書を故意に隠したりすると、相続人の欠格事由あたり、相続人としての地位を失う可能性があります(891条5号)。
遺言書を発見した場合は、速やかに他の相続人に連絡し、今後の相続手続きについて相談しましょう。
相続財産の調査方法に関するQ&A(不動産登記簿の場合) 相続登記をしない場合にデメリットはありますか?