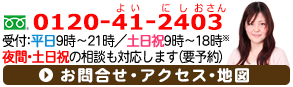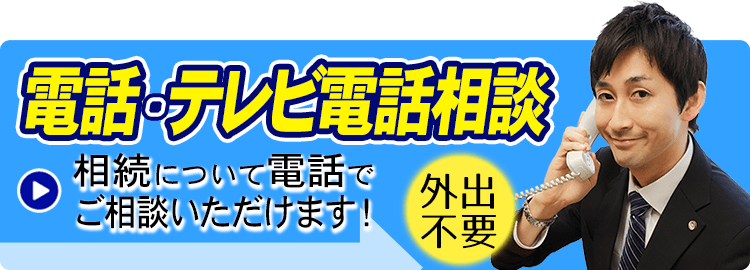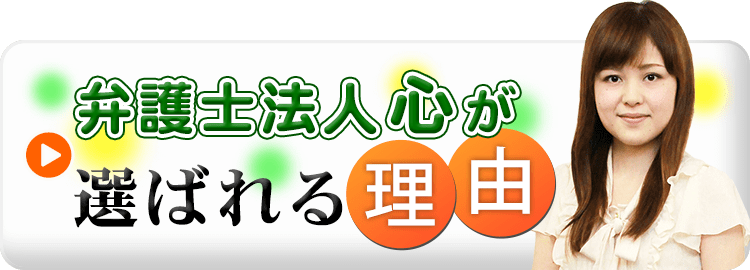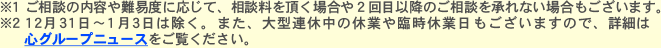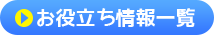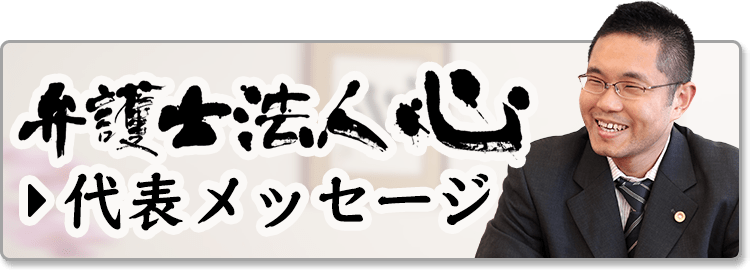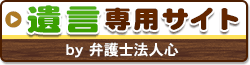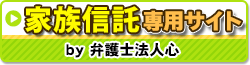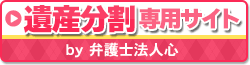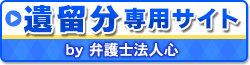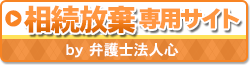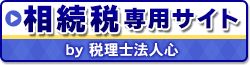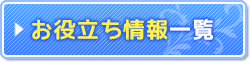限定承認
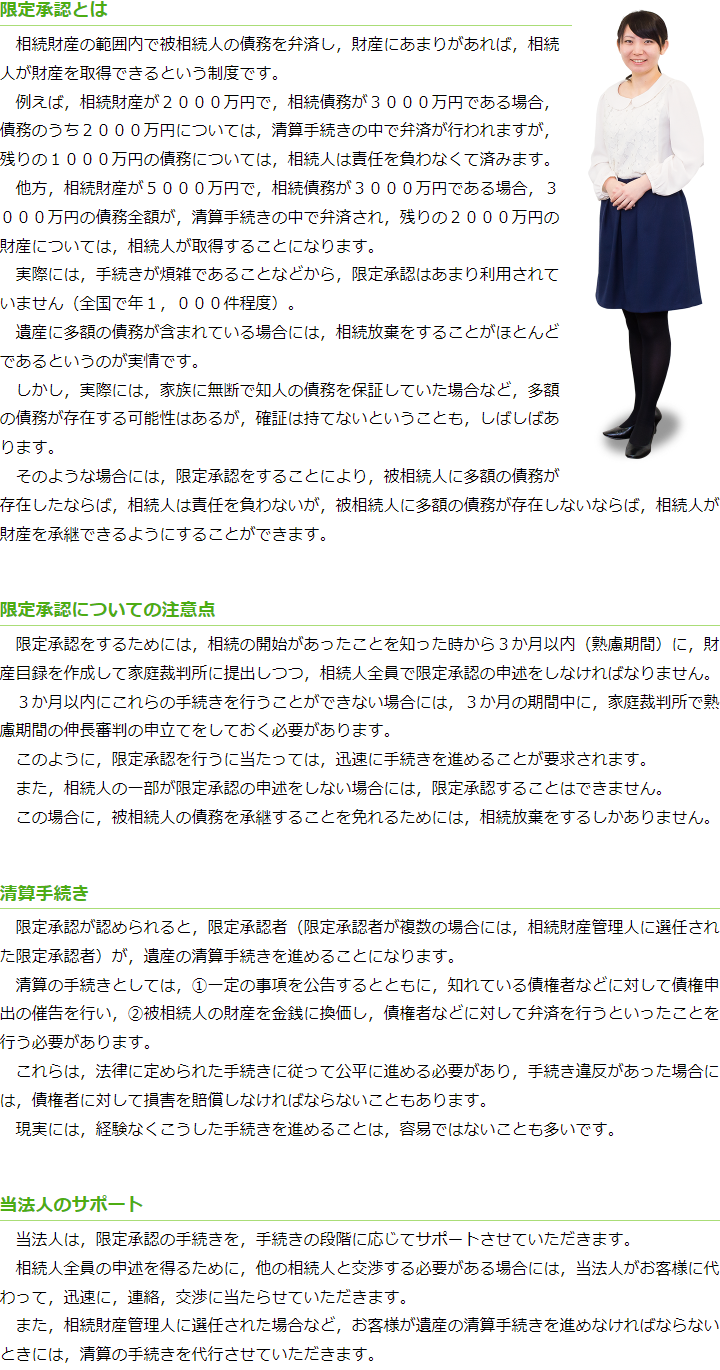
限定承認と相続放棄の違い
1 限定承認と相続放棄

限定承認も相続放棄も、相続人となった場合に、どのように相続するか(あるいは相続しないか)について選択する制度になります。
いずれも、必ず、家庭裁判所で申述手続を行うことにより、制度を利用することができます。
限定承認と相続放棄は、まったく異なる制度ではありますが、ここでは、相続人となった人にとって、どのような違いをもたらすかについて、説明したいと思います。
2 負うべき責任、相続することができる財産の違い
相続放棄をした人は、被相続人が負っていた債務について、一切の責任を負わないこととなります。
反面、財産についても、一切引き継ぐことができないこととなります。
限定承認をした人は、被相続人が負っていた債務について、被相続人が有していた財産の限度で、責任を負うこととなります。
つまり、被相続人が有していた財産からは、弁済する責任を負うこととなりますが、相続人個人の財産からは、弁済する責任は負わないこととなります。
このように弁済を行った結果、被相続人の債務が残った場合(つまり、被相続人の財産より債務が多かった場合)は、残債務については、相続人が弁済する責任は負いません。
他方、弁済を行った結果、被相続人の財産が残った場合(つまり、被相続人の債務より財産が多かった場合)は、残った財産については、相続人が引き継ぐことができます。
このように、相続放棄は、被相続人の債務も財産も一切引き継がないのに対し、限定承認は、被相続人の財産の限度で債務を弁済すべきこととなります。
3 手続を選択できる人の違い
相続放棄については、各相続人が相続放棄をするかどうかを決めることができます。
他に相続放棄をしない相続人がいたとしても、法律上は自由に相続放棄をするかどうかを決めることができます。
他方、限定承認については、相続人全員で限定承認することを選択して、手続を行う必要があります。
一部の相続人が限定承認に反対である場合は、限定承認の手続を行うことはできません。
ただ、一部の相続人が相続放棄を行った場合は、その人は最初から相続人ではなかったものと扱われますので、相続放棄をしなかった相続人全員で限定承認の手続を行うことができます。
4 後順位相続人への影響の違い
相続放棄を行った場合は、相続放棄を行った人が最初から相続人ではなかったこととなる結果、新たに後順位相続人が相続人になってしまう可能性があります。
たとえば、当初は被相続人の子が相続人となっていた場合に、被相続人の子が全員相続放棄を行った場合には、被相続人の父母が相続人になります。
被相続人の父母が存命でない場合や、被相続人の父母も全員相続放棄を行った場合には、被相続人の兄弟姉妹や甥姪が相続人となります。
このため、新たに、被相続人の債務等を引き継いだりすることとなる親族が現れる可能性があります。
新たに相続人となった親族が家庭裁判所で相続放棄の申述を行えば、この親族も債務等を引き継がなくて済むこととなりますが、申述を行わなかった場合には、債務等を引き継ぐこととなってしまいます。
限定承認を行った場合には、限定承認をした人が相続人のままであることとなり、限定承認をした人が財産の限度で債務を弁済する手続を行うこととなりますので、後順位相続人が新たに相続人になることはありません。
5 後続手続の違い
相続放棄の場合は、相続放棄の申述が家庭裁判所で受理されると、手続が終了することとなります。
相続放棄をした人が、被相続人の債務を弁済したり、被相続人の財産を管理、売却したりする必要はありません。
よく、物事を分かっていない専門家から、相続放棄をした後も、財産に対する管理義務が残るという話がなされることがありますが、現に占有している財産に限る話ではありますので、このような事情がなければ、財産を管理する義務は負わないこととなります。
他方、限定承認の場合は、限定承認の申述が家庭裁判所で受理された後も、手続が続くこととなります。
具体的には、限定承認の申述がなされた旨の公告を行った上で、相続財産を管理し、順次、現金化が可能であるものは、現金化します。
相続財産の中には、現金化が困難であるものが含まれていることがありますが、このような場合には、現金化等の目途を付けるまで、限定承認の手続は終わらず、その間、財産を管理する責任を負い続けることとなります。
公告の期間が経過し、一通りの財産の現金化が完了すると、現金化した財産の範囲内で、債権者に対する弁済を行います。
このように、限定承認については、申述後も、相続財産を現金化し、債権者に対して弁済する手続が継続することとなります。
このような手続を適切に行うためには、十分な知識と経験が必要になりますので、限定承認については、経験のある専門家に依頼しなければ、適切に手続を行うことは困難であると考えられます。