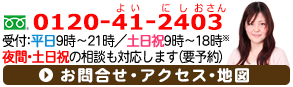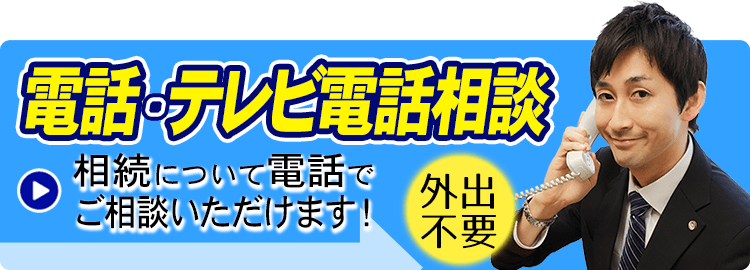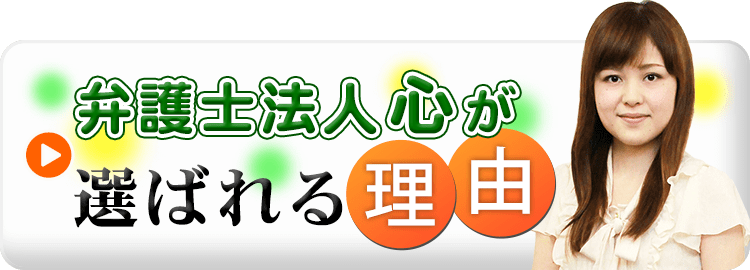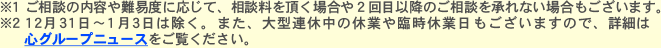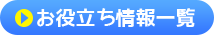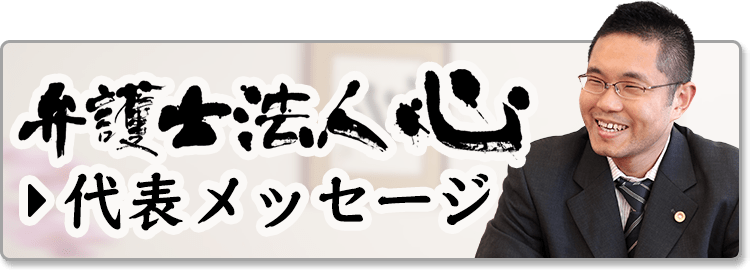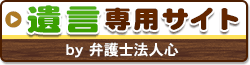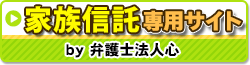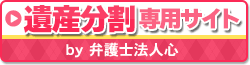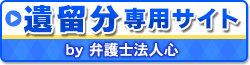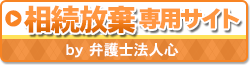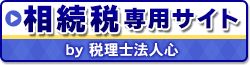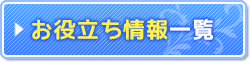相続人調査
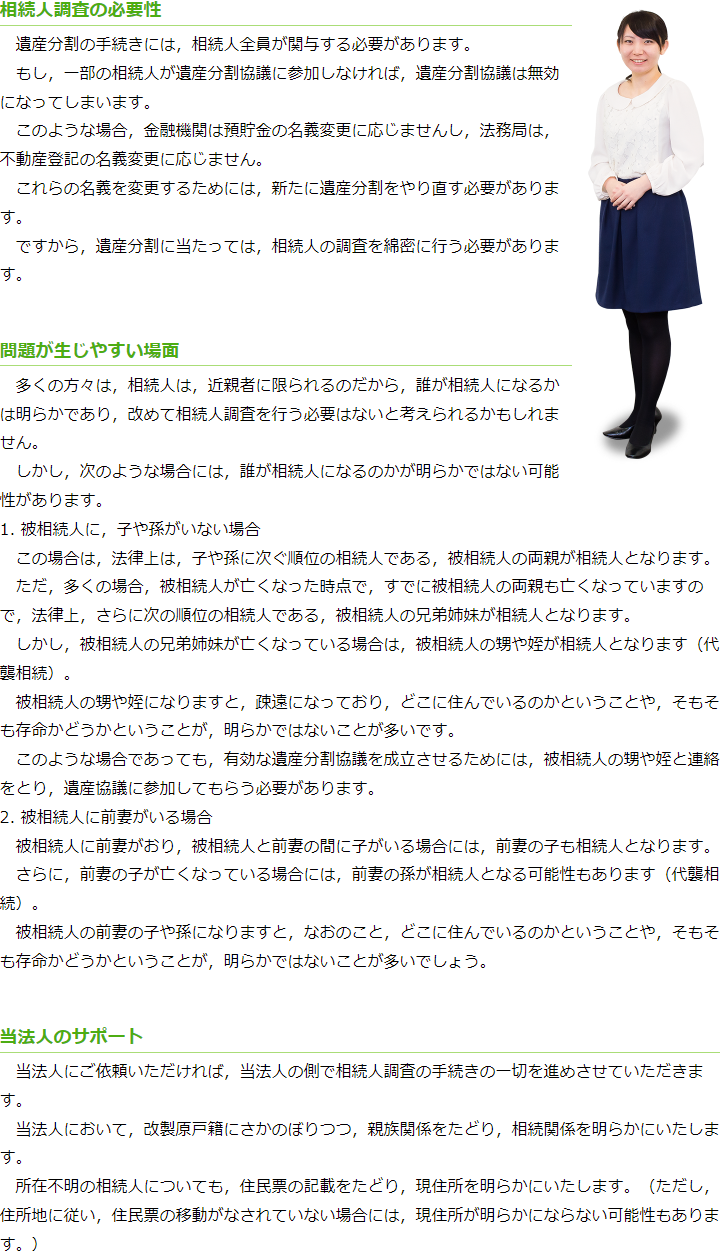
弁護士による相続人の調査
1 戸籍、住民票の調査

相続人の調査を行う場合、まずは、戸籍、住民票の調査を行います。
- ⑴ 戸籍
-
相続関係を公的に証明する場合には、戸籍を利用します。
戸籍以外の書類では、基本的には相続関係を証明できないこととなっています。
このため、相続人が誰であるかを確認する手段として、戸籍を取得することが必要不可欠となります。
取得する必要のある戸籍は、誰が相続人になるのかによって異なります。
例を挙げると、以下のとおりです。
・被相続人の子が相続人になる場合
被相続人の出生から死亡までの戸籍
子の現在の戸籍
・被相続人の子がすでに亡くなっており、被相続人の孫が相続人になる場合
被相続人の出生から死亡までの戸籍
子の出生から死亡までの戸籍
孫の現在の戸籍
- ⑵ 住民票
-
相続人が誰であるかが確認できたら、次は、相続人がどこに住所を置いているかを確認します。
住所を公的に証明する場合には、住民票を使用します。
また、戸籍の附票も、住民票と同じ機能を持っていますので、代わりに戸籍の附票を使用することもできます。
このため、相続人の住所を確認する手段として、住民票か戸籍の附票を取得します。
- ⑶ 戸籍・住民票の取得方法
-
戸籍や住民票、戸籍の附票については、これらの書類を管理している市役所で取得します。
戸籍、戸籍の附票については、これらが作製された当時の本籍地の市区町村役場で管理されています。
住民票については、住民登録がなされている住所の市区町村役場で管理されています。
2 戸籍が取得できない場合
古い戸籍については、戦災や災害等で消失するなどして、残っていないことがあります。
このような場合には、市区町村役場で、戸籍が残っていないことを証明する焼失証明書、滅失証明書と呼ばれている証明書の発行を受けることができます。
その上で、戸籍では確認できない相続人の調査を試みることとなります。
過去には、お寺の過去帳や関係人からの聞き取りで相続人が誰であるかの確認を試みた例もありますが、過去帳自体を公的な証明として用いることはできません。
そのため、こうした情報を手がかりとして、家庭裁判所で戸籍訂正申立等の手続きを行い、訂正後の戸籍を入手する必要があります。
しかし、多くの事例では、こうした手がかりとなる情報を手に入れることすらできません。
このため、戸籍に記載のない相続人については、存在しないとの前提で、手続きを進めるより他ないことがほとんどです。
法務局や金融機関でも、現在では、戸籍に記載のない相続人については存在しないとの前提で、相続の手続きを進めることができることとなっています。
3 住民票では住所を特定することができない場合
一般に、住所変更があった場合には、住民票上の住所も変更されますが、住所変更があったのに住民票上の住所が変更されていないケースもゼロではありません。
この場合には、住民票を取得できたとしても、その相続人はそこに住んでおらず、その相続人の住所を確認することができないこととなります。
住民票では住所を特定できず、親族等から住所を確認することもできない場合には、相続人が所在不明となってしまいます。
相続人が所在不明であったとしても、その相続人を手続きに関与させなければ、相続の手続きを完了させることができません。
相続人が所在不明である場合の対処法として、不在者財産管理人選任申立を行うことが多いです。
不在者財産管理人選任申立を行うと、家庭裁判所は、ハローワーク、警察、年金事務所等に、所在に関する情報がないか、照会を行います。
このような照会により、相続人の住所が特定できることがあります。
他方、こうした照会によっても相続人の住所が特定できない場合には、所在不明者のままとなりますので、不在者財産管理人が選任され、不在者財産管理人が代わりに相続の当事者となります。