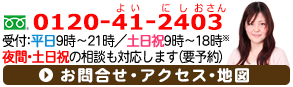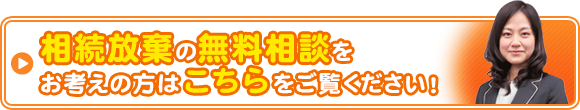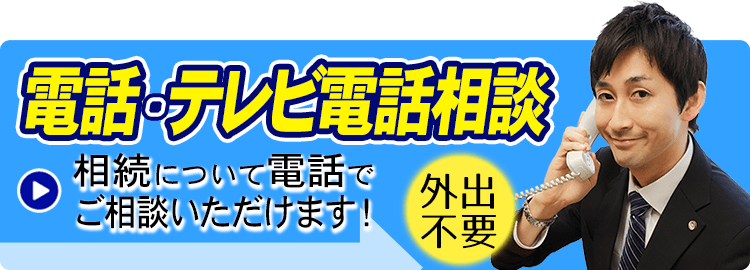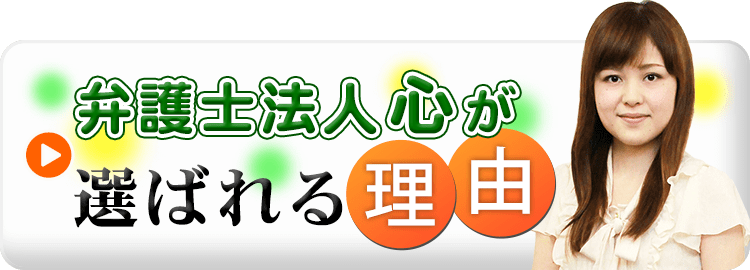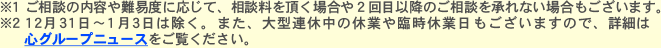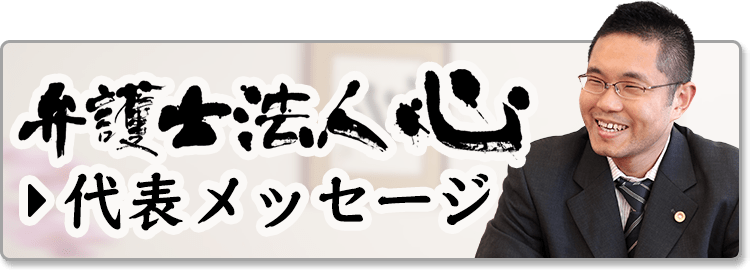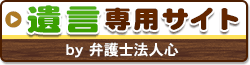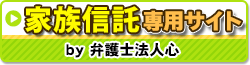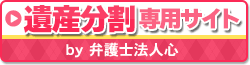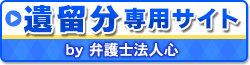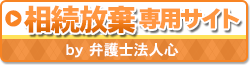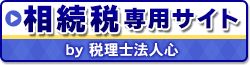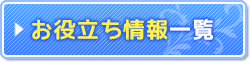相続放棄申述受理証明書を申請する方法
1 相続放棄申述受理証明書を申請する方法
相続放棄申述受理証明書は、相続放棄の申述がなされた裁判所、つまり、亡くなった人(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、申請書、添付書類、手数料として1通あたり150円の収入印紙を提出することで発行することができます。
これら申請に必要な書類等についての提出方法は、裁判所への郵送でも窓口への持参でもどちらでも可能です(メール等電子申請の方法は現在取扱いが原則ありません)。
このとき、提出先については、管轄があることに注意してください。
2 相続放棄申述を行った相続人の場合の必要書類
① 申請書
家庭裁判所の窓口又は家庭裁判所のホームページにデータありますので、窓口にて取得していただくか、ホームページからダウンロードをして印刷の上、ご提出ください。
記載内容は簡単なものですので、書類を見ながら、記載を進めていただければと思います。
参考リンク:裁判所・手続案内
また、この申請書は、相続放棄申述受理手続き時に、相続放棄手続きが完了した旨知らせる「相続放棄申述受理通知書」と一緒に交付される場合もありますので、それを利用することができます。
申請書には押印をする場所もありますので、窓口で、手続きを行う場合は、印鑑も持参する必要があります。
② (代理人を利用する場合)委任状
原則弁護士以外の人は代理人になれません。
③ 返信用封筒
裁判所からの申請書を受け取るための封筒になります。
返信先の住所と宛名を記入し、切手代を貼付したものを同封してください。
3 相続人が申請する場合の必要書類
申述人以外の相続人が相続放棄申述受理証明書を取得する場合は、以下のものが必要です。
① 申請書
相続放棄をした者以外の場合、裁判所から相続放棄申述受理についての事件番号を記載する必要があります。
事件番号は、相続放棄申述受理通知書を確認していただくか、別途事件番号の照会を行うための「相続放棄・限定承認の申述の有無の照会」を行う必要があります。
この「相続放棄・限定承認の申述の有無の照会」は基本的に相続放棄申述受理証明書発行と同じ添付資料に、「相続人目録」を添付することで行うことができますので、今回の必要書類を参考にしてください(照会に手数料はかかりません)。
また、申請時には、相続放棄申述についての回答書を提出する必要があります。
② 被相続人の死亡したことが記載されている戸籍(全部事項証明書)
③ 被相続人の最後の住所地の住民票除票(本籍地の記載があるもの)又は戸籍の附票
④ 申請者が被相続人の相続人であることが分かる戸籍・除籍・改製原戸籍謄本(発行から3か月以内のもの)
⑤ 申請者の本人確認資料の写し
代理人を利用する場合は、その代理人の本人確認ができる資料(住民票等)の写しが必要になります。
⑥ (代理人を利用する場合)委任状
⑦ 返信用封筒
4 利害関係人が申請する場合の必要書類
相続人以外の人が相続放棄申述受理証明書を取得する場合は、以下のものが必要です。
① 申告書
2と同じです。
② 資格証明資料
A(申請者が法人のとき)代表者事項証明書等(発行から3か月以内のもの)
法人の場合は、代表者が申請者となる場合が多いですが、その代表者であることが分かる証明書が必要となります。
ただし、銀行等の支店長は、登記が行われている支配人でない限り、できない場合があります。
B(個人のとき)申請者本人確認資料の写し
③ 利害関係疎明資料
利害関係の内容、利害関係人の住所及び氏名、被相続人の住所、氏名及び生年月日等を確認できる契約書、不動産登記事項証明書、判決書等の写しが必要です。
書類だけでは利害関係が不明な場合は、説明書を作成し、添付することも可能です。
④ 被相続人情報確認資料
A 被相続人の死亡したことが記載されている戸籍謄本
B 被相続人最後の住所地が記載されている住民票除票
⑤ (代理人を利用する場合)委任状
⑥ 返信用封筒
遺留分侵害額請求の流れ 相続放棄の管轄裁判所はどこになるのか